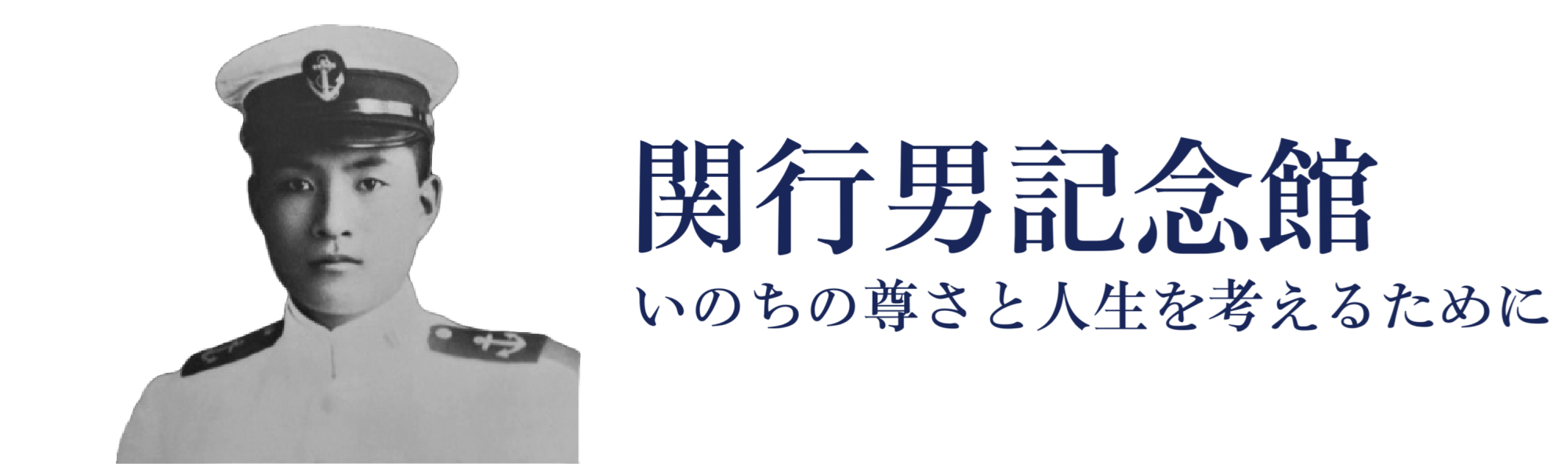卒業しては殺されていく
日米開戦直前の卒業になったばかりに
■日米開戦直前に海軍兵学校を卒業された方々が、戦争でどれだけ亡くなられたか| 第65期 | 1934. 4. 1入学 1938. 3.16卒業 | 卒業187人 戦死106人 | 戦死率56.7% | |
| 第66期 | 1935. 4. 1入学 1938. 9.27卒業 | 卒業220人 戦死119人 | 戦死率54.1% | |
| 第61期からの戦死率が50%超で推移したため、定員を増やすと同時に士官の早期養成を画策します。 入学時期を早めて在校期間も短縮を決めました。第66期は9月に卒業させ、3か月後の12月に新入生を入校させました。この最初が第70期生で、彼ら以降の入校時期は本来4月だったものが前年12月に繰り上げられます。 |
||||
| 70 期在学 |
||||
| 第67期 | 1936. 4. 1入学 1939. 7.25卒業 | 卒業248人 戦死155人 | 戦死率62.5% | |
| 第68期 | 1937. 4. 1入学 1940. 8. 7卒業 | 卒業288人 戦死191人 | 戦死率66.3% | |
| 第69期 | 1938. 4. 1入学 1941. 3.25卒業 | 卒業343人 戦死222人 | 戦死率64.7% | |
| 第70期 | 1938.12. 1入学 1941.11.15卒業 | 卒業433人 戦死287人 | 戦死率66.3% | |
| →1941.12.8の日米開戦に間に合うよう卒業させる | ||||
参拾壱頁(海軍兵学校・機関学校・経理学校卒業者数一覧)から抜粋・加工
士官になる夢が死に直結していく
最初に特別攻撃隊の隊長を担われた関行男海軍中佐。最後の特別攻撃隊の隊長を担われたのは中津留達雄海軍少佐、おふたりとも海軍兵学校(士官学校)の卒業生、第70期の同期生です。
海軍兵学校はいわば海軍の士官学校です。「兵学」を学ぶ学校という意味です。陸軍士官学校とともに、第一高等学校(東京大学教養学部の前身)以上の難関と言われました。高等学校が学力を中心に入学者を選抜するのに対して、体力や人格、体格や身体検査も含めて合否が決まります。学力も体力も鍛え上げて卒業すれば少尉候補生となり、士官としての人生を歩みます。海軍兵学校の入学者数や、修了年数、入学卒業時期、そして戦死率を見るとき、大東亜戦争・太平洋戦争に関わられた方々が、いかに厳しい時代に投げ出されたかが垣間見えます。
戦争の苛烈さは戦死率という指標にいちばん明確に現れ、1933年以降50%を超えました。
戦死率の上昇に呼応して定員を徐々に増やす一方、修了年限を短縮していき、1932年以降4年あったものが、1935年から3年3~6か月となり、1938年(第69期)には3年で卒業となりました。
1学年分校舎が空くわけですから、第70期から5か月繰り上げて冬入学とし、早く下士官を養成しはじめ、早く卒業させ戦地へ送る。相当に海軍が焦っていたということの表れです。
1941年には「勝利の基礎(いしずえ)」という海軍兵学校の学校生活を描いた映画が制作されました。この映画に登場するのがほかでもなく海軍兵学校第70期生たちです。広島県の瀬戸内海に浮かぶ江田島を舞台にした青春群像を通して、海軍士官への憧れをかき立てる内容になっています。
その第70期生が在校中、既に卒業して前線に出た方々の戦死率は強烈です。第70期の直前の3期(1939年から1941年の卒業生)は、戦歿士官の激増により入学生を倍増、3倍増にしながら、戦死率は62%から66%に跳ね上がります。
どれだけ多くの下士官の方々が戦歿されたか。そして前線の指揮を任された方々が死ぬると言うことは、その何倍もの兵士達も大変なことになっているということです。どこをみても惨状が繰り広げられているというのは容易に想像がつきます。
そして、第70期卒業生は66.3%が戦死なさるに至りました。1939年以降の卒業生が投入され、戦死率が高率で推移したままということは、年数が経過しても何ら状況が好転しなかったということ。
まずは裕仁、そしてまとわりつく指揮系統が、敵国とした相手も学び強くなっていく、凌駕していくということすら軽視して戦争を仕掛ける無謀さ。挙げ句国力の差に圧倒され、ただ手をこまねくだけの無能さと無責任さ。
ただただその結果、国民の死体の山を築き上げただけのどうしようもない人間がこの世を支配していたことが、この国にとっての悪夢であったと思います。